文化庁の「国語に関する世論調査」*によると1ヶ月間に本を1冊も読まないとした人は、2023年度で62.6%、2018年度の47.3%から大きく増えたそうです。
それを受けてか、いろんなメディアや書籍でも「本を読んだ方がいいよ」というメッセージが以前より強くなってきている気がします。
私は小さい頃から本が好きで、本の虫とまではいきませんが、いつもポツポツと本を読んでいます。
そこで本を読むメリットや読書がもたらす効果について、齋藤孝さんの著書『読書する人だけがたどり着ける場所』で学びたいと思いました。
結論から言うと、本の題名である読書する人だけがたどり着ける場所というのは、読書体験によって人格や人生を形成して、より深みのある場所にたどり着けるということだと思います。
読書しなくてもネットで情報が取れるという人もいますが、齋藤さんはこの二つの違いについて、ネットで読むことは「消費」であってすぐ忘れてしまうもの、一方で読書は体験であり、それが人格形成を促すとしています。
深い人というのは教養のある人のことで、教養=知識ではなく、知識に基づいて本質を理解したり、自分の考えを持つ人です。
この本で特に学びがあった部分は以下の3点。
AIに負けないことを目的に生きるなんて本末転倒
2045年には人工知能が人間の脳を超えるシンギュラリティ(技術的特異点)に達すると言われています。
AIに仕事を奪われないためにはどうしたらいいかや、AIにできないことをできるようにするには?というテーマをよく耳にしますし、夫とも将来に残る職種について話したりもします。
しかし『AIが出てこようが出てこなかろうが、「自分の人生をいかに深く生きるか」が重要なのではないでしょうか。』という齋藤さんの一言にハッとさせられました。
AIについて理解したりするのは素晴らしいけれども、自分の判断基準をAIにしてしまうことこそ、AIに侵略されているなと感じました!
物語で身に付く「映像化」する力
物語を読むことで風景や人物の姿を想像したりする。
この時、脳はとても高度な働きをしていると言います。今まで小説はエンターテイメントだと思っていたので、ここで物語の凄さを再確認できました。
アニメやドラマも楽しいけど原作の小説も楽しいってこの感覚なんだろうなと。
たまに小説が映画化されて、想像してた主人公と違う!とかぴったり!とかってなるのも面白いですよね。
私は割合としてはビジネス書の方を多く読んでいるので、もっと小説も読んでいこうと思います。
文学のすごさはあらすじにあらず!クライマックスを音読すべし!
よく「あらすじでわかるカラマーゾフの兄弟」というような、有名文学のあらすじだけを説明した本があります。
あらすじだけでも知っておくといいのはもちろんですが、齋藤さんはできたらクライマックスを音読するのをおすすめしています。
一流の文学にはとんでもない力が宿っていて、著者や登場人物になりきって音読すると心情や行間の意味がとても理解しやすいそうです。
音読なんてしたこともないし、しようと思ったこともなかったのでびっくり!
確かに想像してみると、村上春樹の小説とかも音読したらすごく良さそう!これはぜひ試してみたいと思いました。
この本の中にはたくさんのおすすめ名著も紹介されているので、この後はこれらの名著をじっくり味わって自分の血肉にしたいと思います。
一言まとめ
「読書体験によって人格形成し深みを作ろう」
*参考サイト:読売新聞オンライン

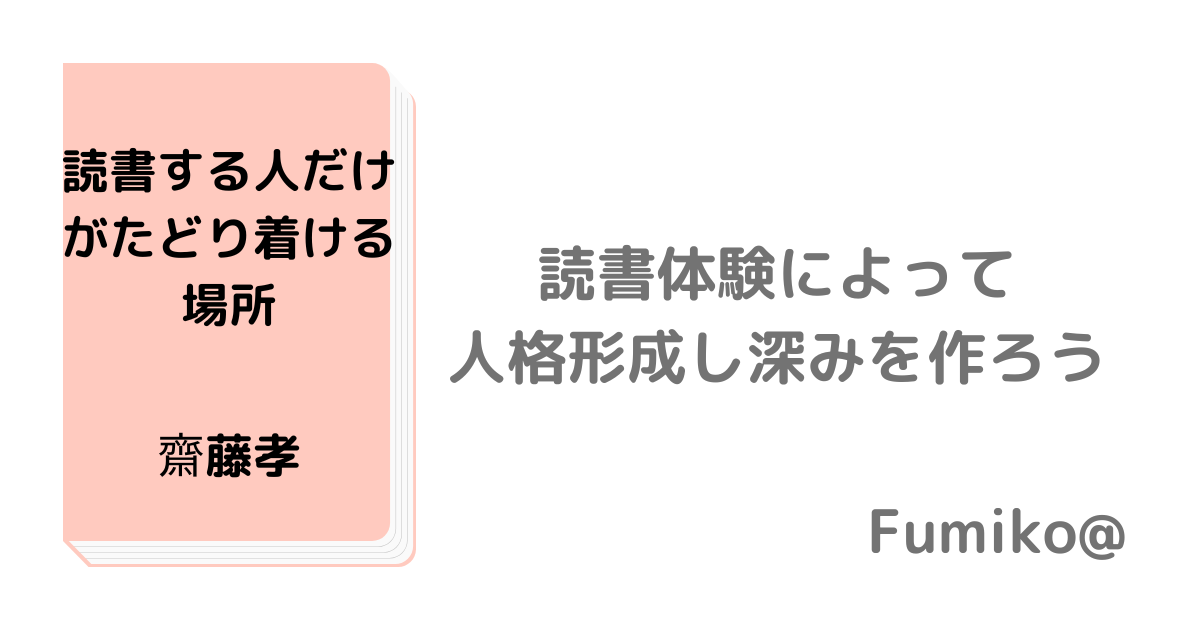
コメント